ご存知、タイヤのトレッド面をじっくり眺めると、溝の奧の所々に凸形状のスリップサインが確認できます。
タイヤのトレッドが摩耗し、1箇所でもスリップサインが出ていたらアウト。そのタイヤは道路運送車両法上、使用禁止。その時の残り溝は1.6mm。もちろん、車検に通りません。
とこが、タイヤの溝の深さが1.6mm超であれば、古いタイヤでも法的には問題は無く、車検に通ります。
一般的にタイヤの残り溝の深さを基準にして、タイヤ交換が必要か否か決められる事が多いと思います。
そして、まだタイヤの残り溝があっても、新品時から一定の年数が経過していると、安全を取ってタイヤ交換を検討する場合もあります。
愛車の所有期間をトータルで考えると、以下の条件によってタイヤ交換の時期が変わってきます。
・タイヤの残り溝の深さ
・タイヤの使用年数
そして、
(+α)あと何年、愛車に乗って車を買い換える予定なのか?
自動車の平均使用年数が年々、伸びているため、今までのタイヤ交換の基準に加えて、「プラスα」の交換基準を加えてもいいと思うのです。
どちらのタイヤが危険?
ここで、2種類のタイヤを挙げてみると、いったいどちらのタイヤが危険?
| – | タイヤの
残り溝の深さ | 新品時からの
経過年数 |
| Type 1タイヤ | 2mm
(2.5分山) | 3年 |
| Type 2タイヤ | 5mm
(6.2分山) | 6年 |
※新品タイヤの残り溝の深さは8mmとします。
※タイヤの種類は一般的な乗用車用タイヤ。
タイヤの残り溝と使用年数

Type 1タイヤ
上の表の「Type 1タイヤ」は、タイヤの残り溝の深さが2mmで新品時から3年経過しています。
このタイヤを装着している車は比較的、年間走行距離が多いと言えます。年間走行距離が多いという事は、雨天時の走行も多くなります。
一般的に、新品時から3年経過している標準的なタイヤは、まだゴム質がしなやかさを保っている事が多いと思います。
しかし、タイヤの残り溝の深さが2mmとなると、ドライグリップの低下はもちろん、雨天時の危険性が増します。
「Type 1タイヤ」は残り溝が2mmあるため、車検には通ります。しかし、「Type 1タイヤ」は雨の日を含めて安全ではありませんし、明らかに要交換と言えます。
Type 2タイヤ
表の「Type 2タイヤ」は、まだ残り溝が5mm。
雨天時のタイヤの排水性能はまだOKでしょう。しかし、「Type 2タイヤ」は新品時から6年経過しています。
この「Type 2タイヤ」を装着している車は、明らかに年間走行距離が少ないと言えます。
タイヤが製造されてから6年経過していると、タイヤのサイドウォールやトレッド面にヒビ割れが発生しているかもしれません。タイヤは新品時から5~6年経過すると、タイヤ全体のゴム質が硬化してきます。
中には、タイヤの残り溝の深さが十分であっても、新品時から10年前後経過しているタイヤも存在します。このようなタイヤは硬くなってカチカチな状態。それにしても、タイヤの耐久性には驚きです。
新品タイヤに交換して走り出すと、タイヤのしなやかさと乗り心地の良さを感じます。これは、新品タイヤがしなやかなのは当然ながら、今まで履いていたタイヤのゴム質が硬化していたため、走りと乗り心地が悪化していたのです。
タイヤのゴム質は年数をかけてゆっくりと硬化していくため、オーナーはその変化に気付きにくいもの。
Type2タイヤも要交換
タイヤの残り溝がまだ十分であっても、製造されてから年数が経過するほどゴム質が硬化し、ドライとウエット路面共にグリップ力が低下します。スタッドレスタイヤも同様。
また、古いタイヤを履いていると、タイヤから乗員にゴロゴロ感が伝わってくるようになります。これは、タイヤ全体とトレッド面のブロックの硬質化が原因。あと、トレッドの偏摩耗の影響もあるかもしれません。
「Type 2タイヤ」は残り溝が5mmあるため、車検には問題ありません。しかし、トータルで考えますと、「Type 2タイヤ」も快適で安全とは言えませんし、交換を検討すべきでしょう。
低偏平ワイドタイヤの増加

管理人が20代の頃、タイヤサイズが「205/60R15」であれば、スポーツタイヤに属していました。普通のセダンが「185/70R14」なんてタイヤを普通に履いていました。
その後、徐々にタイヤとホイール径のインチアップのトレンドが押し寄せてきました。
今や15や16インチタイヤのホイールが小径に見えてしまい、標準で17や18インチホイールを採用する車種が増えました。
車種によっては、タイヤサイズが225/55R16、225/50R17、225/45R18。ラクシュアリーカーやスポーツカーは、それ以上のサイズのタイヤを履いています。
タイヤのトレンドは太く極薄。
ワイドな低偏平タイヤはタイヤの限界性能が高くなります。
しかし、ワイドな低偏平タイヤは路面との接地面が前後方向にショート化し、横方向にワイド化します。摩耗したワイド&低偏平タイヤは特にウエット性能が大きく低下します。
YouTube動画(ウエット旋回ブレーキテスト)
摩耗した高性能タイヤはウエット性能の低下が見られます。
特に、ワイドタイヤを履く軽量なスポーツカーは速度域によってハイドロプレーニング現象が発生しやすく、雨に弱くなります。フロントが軽いRRやMRは、それが顕著。
逆に、重量級の大型トラックは雨のハイドロプレーニング耐性が高いと言えます。
伸び続ける自動車の平均使用年数
時代と共に、日本国内の普通車の使用年数が伸び続けています。
一般財団法人、自動車検査登録情報協会(自検協)のデータによりますと、乗用車の平均使用年数(※)は平成29年のデータで乗用車計が「12.91年」。もうすぐ13年に達するデータです。
(※)日本国内で自動車が新規登録されてから抹消登録するまでの平均年数。
もちろん、途中で車のオーナーが変わることがあるものの、新車登録されてから登録が抹消されるまでの年数が伸び続けているは確か。
それだけ、自動車の信頼性と耐久性が高まってきた証であり、オーナーは長く愛車に乗る傾向が強まっていると言えます。
新車購入後、2~3年以内で車を乗り換えるオーナーであれば、タイヤを交換する必要性は低いかもしれません。しかし、オーナーが5年、7年、9年と愛車に乗り続けるならば、必ずタイヤ交換が必要。
そこで、どのタイミングでタイヤ交換するのが適切なのか考えてみます。
タイヤの交換時期
冒頭のとおり、まだタイヤの残り溝があっても、快適で安全とは言い難いタイヤも存在します。そこで、新車、中古車を問わず、安全性を含めた合理的なタイヤ交換の時期を考えてみます。
もちろん、タイヤの寿命はタイヤのブランドや走行条件、車種等によって変わってくるため、どの時点でタイヤを交換したらいいのか一概には言えません。
特に、ハイパフォーマンスカーは車重が重く、エンジン出力が高いため、タイヤの寿命が短くなる傾向があります。
以下のシミュレーションは、CからDセグメントを想定して、タイヤの寿命を30,000~40,000kmで仮定しています。
「■」は自動車を購入してから1年を意味します。
5年で車を買い替える場合
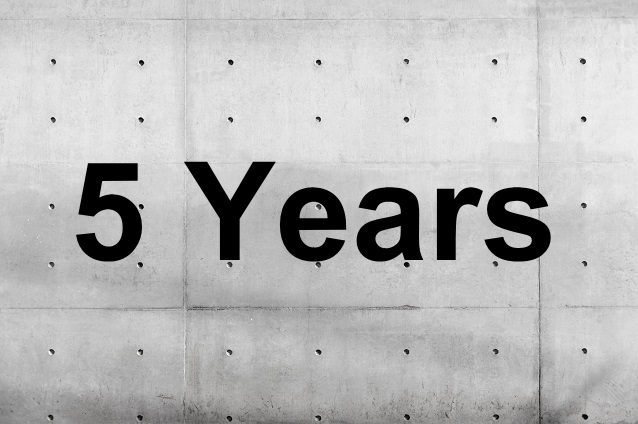
■新車購入の場合
■■■■■|→車の買い替え
——↑↑–
タイヤの交換時期の目安(3年目、または4年目)
[年間走行距離が6,000~7,000km]
年間走行距離が6,000~7,000km以内であれば、タイヤは無交換のまま車を買い替える時期を迎えるかもしれません。あるいは、4年目以降、タイヤ交換を検討するオーナーがいるかもしれません。
[年間走行距離が10,000km]
年間走行距離が10,000km前後であれば、新車購入から3年~4年経過した時点でタイヤ交換の必要性が出てきます。
新車購入から4年経過した時点でタイヤを交換すると、新品タイヤを履いている期間はわずか1年。
新車から3年経過した時点でタイヤを交換しても、5年間という車の所有期間の中でタイヤ交換に必要な経費は変わりません。とすると、3年経過した時点でタイヤ交換した方がお徳と言えます。
タイヤは生ものと言われ、旬の期間はそれほど長くはないので。
■中古車購入の場合
■■■■■|→車の買い替え
—-↑↑—-
タイヤの交換時期の目安(2~3年目以内)
中古車の場合、タイヤの摩耗状態は千差万別。新品タイヤに交換後、納車されるのであれば話は別ながら、タイヤの残り溝が5分山と仮定して考えてみます。
[年間走行距離が6,000~7,000km]
・年間走行距離が6,000~7,000km以内であっても、5年という車の所有期間の中でタイヤ交換の必要性が出てきます。中古車を購入後、2~3年以内にタイヤ交換が必要になります。
[年間走行距離が10,000km]
・年間走行距離が10,000km前後であれば、中古車の購入から比較的早い時期にタイヤ交換の必要性が出てきます。頃合いを見てタイヤ交換となります。
7年で車を買い替える場合
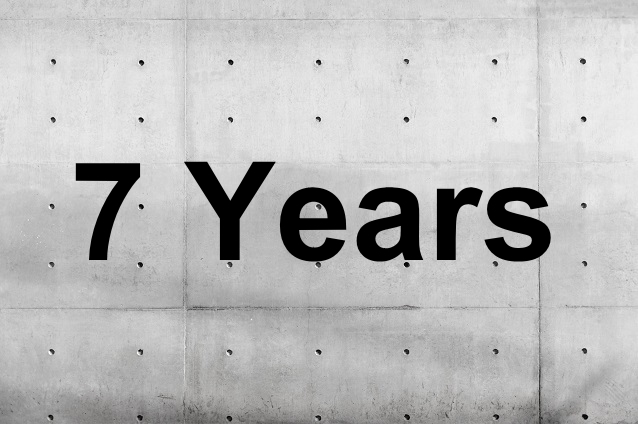
■新車購入の場合
■■■■■■■|→車の買い替え
——-↑↑—–
タイヤの交換時期の目安(3~4年目)
[年間走行距離が6,000~7,000km]
・年間走行距離が6,000~7,000km以内の場合、新車購入から4年目あたりがタイヤ交換の目安になるでしょう。
新車購入から5年目でタイヤ交換すると、新品タイヤを履いている期間は2年。でしたら、4年目でタイヤ交換した方がお得ですし、7年の間でタイヤ交換に必要な経費は変わりません。
[年間走行距離が10,000km]
・年間走行距離が10,000km前後であれば、新車購入から3年~4年経過した時点でタイヤ交換の必要性が出てきます。
■中古車購入の場合
■■■■■■■|→車の買い替え
—-↑↑——
タイヤの交換時期の目安(2~3年目以内)
中古車の場合、タイヤの摩耗状態は千差万別。新品タイヤへ交換後に納車されるのであれば話は別ながら、タイヤの残り溝が5分山と仮定して考えてみます。
[年間走行距離が6,000~7,000km]
・年間走行距離が6,000~7,000km以内であっても、7年という車の所有期間の中で必ずタイヤ交換の必要性が出てきます。中古車を購入後、2~3年以内にタイヤ交換が必要になります。
[年間走行距離が10,000km]
・年間走行距離が10,000km前後であれば、中古車の購入から比較的早い時期にタイヤ交換の必要性が出てきます。頃合いを見てタイヤ交換となります。
9年で車を買い替える場合
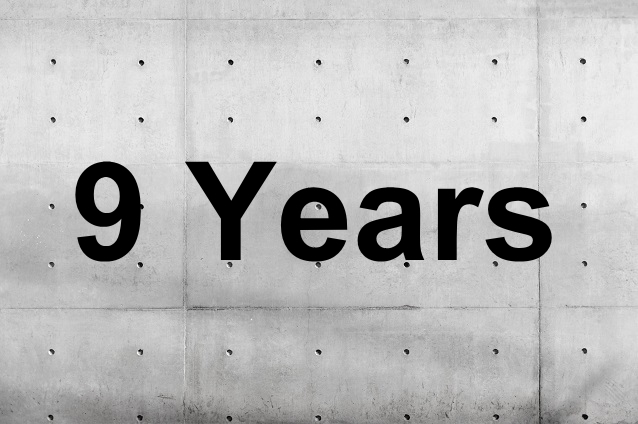
■新車購入の場合
■■■■■■■■■|→車の買い替え
——-↑↑—↑↑—
タイヤの交換時期の目安(3~4年目と6~7年目)
[年間走行距離が6,000~7,000km]
・年間走行距離が6,000~7,000km以内の場合、新車購入から4年目あたりがタイヤ交換の目安になるでしょう。そして、8年目あたりで2回目のタイヤ交換を検討する時期かもしれません。
しかし、新車購入から8年目でタイヤ交換すると、新品タイヤを履いている期間はわずか残り1年。そして、車の買い替え時期を迎えます。
だったら、7年目でタイヤ交換した方がお得ですし、9年の間でタイヤ交換に必要な経費は変わりません。
[年間走行距離が10,000km]
・年間走行距離が10,000km前後であれば、新車購入から3年~4年経過した時点でタイヤ交換が必要です。そして、7年目あたりで2回目のタイヤ交換を検討する時期かもしれません。
■中古車購入の場合
■■■■■■■■■|→車の買い替え
—–↑↑—-↑↑—
タイヤの交換時期の目安(2~3年以内と6~7年目)
中古車の場合、タイヤの摩耗状態は千差万別です。新品タイヤへ交換後に納車されるのであれば話は別ながら、タイヤの残り溝が5分山と仮定して考えてみます。
[年間走行距離が6,000~7,000km]
・年間走行距離が6,000~7,000km以内であっても、9年という車の所有期間の中で必ずタイヤ交換の必要性が出てきます。
中古車を購入後、2~3年以内にタイヤ交換の必要があります。そして、6~7年目に2回目のタイヤ交換の時期を迎えます。
[年間走行距離が10,000km]
・年間走行距離が10,000km前後であれば、中古車の購入から早い時期にタイヤ交換の必要性が出てきます。頃合いを見てタイヤ交換となります。
そして、6~7年目に2回目のタイヤ交換の時期を迎えます。
タイヤ交換時期は(1)溝の深さ(2)使用年数(3)車の所有期間で総合的に決めるのも方法
一般的に、タイヤの交換時期はタイヤの残り溝の深さで決めることが多いと思います。
ところが、タイヤ交換の基準が「残り溝の深さ」だけの場合、タイヤを交換して1~2年後に車の買い替え時期を迎える場合もあると思います。
大雑把に新車、中古車に関わらず、
・愛車を5年間所有するならば、タイヤ交換が1回は必要。
・7年間所有するならば、タイヤ交換が1回以上、あるいは2回必要。
・9年間所有するならば、タイヤ交換が2回以上、あるいは3回必要。
※まだタイヤの残り溝があっても、製造年から5年を目安に交換。
まだタイヤの残り溝があっても、年数経過に比例してゴム質が硬化し、走行性能や快適性、安全性が低下していきます。
新車を買うのか、中古車を買うのか、そして年間走行距離、その他の要因で諸条件が変わってくるため、タイヤ交換時期の話が少々ややこしくなってしまったかもしれません。
要は、タイヤのスリップサインが出る寸前まで無理にタイヤを履き続けると、快適性と安全性が損なわれます。
その後、新品タイヤに交換して1~2年で車の買い替え時期を迎えるとなると、新品タイヤを味わう期間が短くなってしまいます。
まだタイヤの残り溝が残っていても、少々、早めにタイヤ交換したところで、タイヤ交換に必要な経費は変わらないのです。
年間走行距離が少ないオーナーの場合
例えば、年間走行距離が少ないオーナーが10年で車を買い替える場合、その間、タイヤ交換は1回だけというケースがあります。
通勤距離が短いオーナーや車の使用頻度が少ないオーナー、近場の買い物や用事で車を使う年金受給者が該当すると思います。
この場合、6年、7年目でタイヤ交換するよりも、5年目でタイヤ交換した方が快適で安全と言えます。10年という期間で、タイヤ交換の経費は変わりません。
■■■■■■■■■■|→車の買い替え
————-↑↑—
車の購入から6年、7年目でタイヤ交換
VS
■■■■■■■■■■|→車の買い替え
———–↑———-
車の購入から5年目でタイヤ交換
まとめ
いつの時代もタイヤは新しいほど、全ての面で性能が上。タイヤ交換時期は以下の3つの項目で判断すると合理的で安全だと思います。
(1)タイヤの溝の深さ
(2)タイヤの使用年数
(3)車の所有期間
愛車の所有期間を大雑把に決めているのであれば、タイヤの交換時期は残り溝だけではなく、タイヤ交換後に車を何年所有するのか勘案して、タイヤ交換の時期を決めるのも1つの方法かと思います。
[関連記事]













